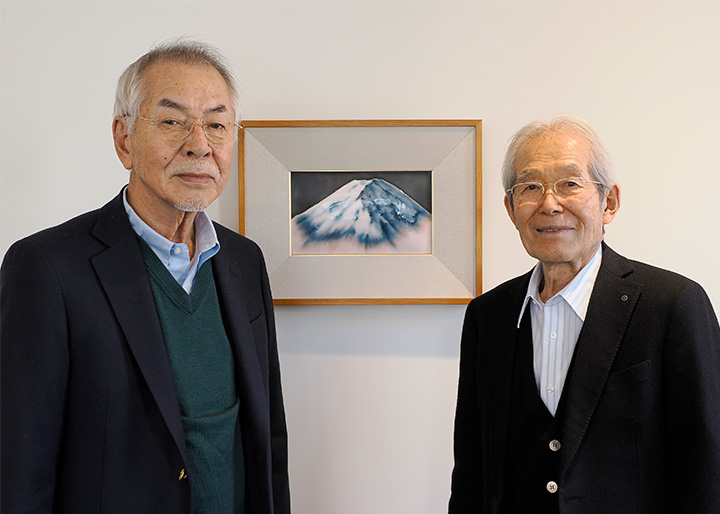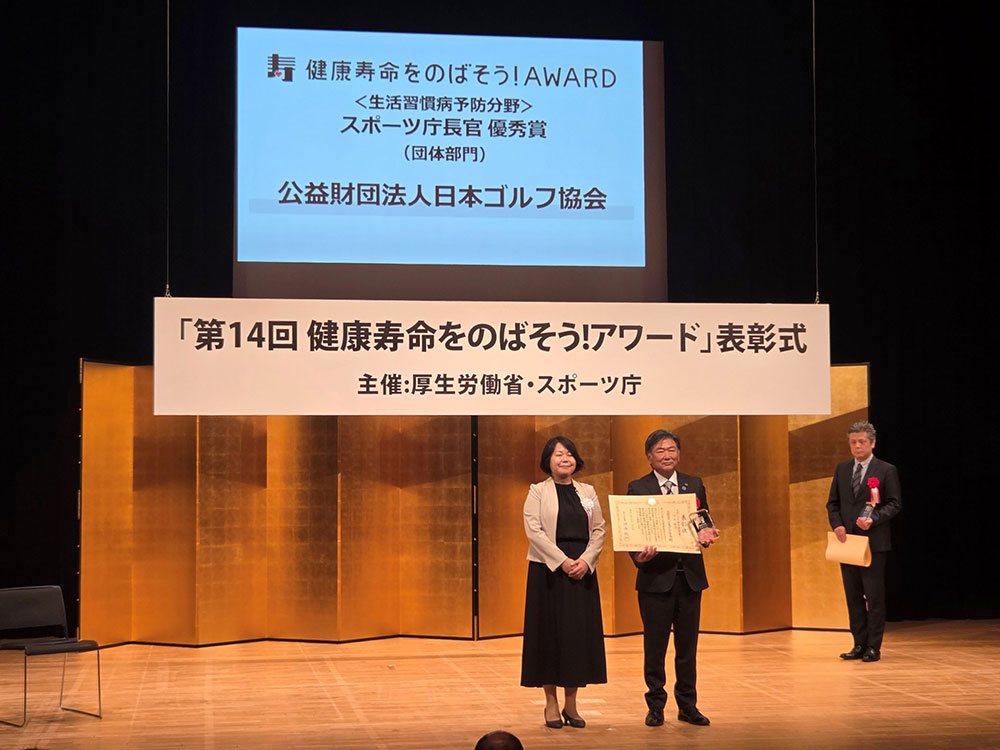日本シニア・ゴルファース協会理事 武内次男さん(右)・同理事 浅井義久さん(左)
日本シニア・ゴルファース協会(JSGA)(関根宏一会長)は、1963年(昭和38年)に発足して以来、アマチュアのシニアゴルファーによる倶楽部を横断した組織として、活動を続けている。また、「日米親善ゴルフ大会」や「ワールドシニアチャンピオンシップ」に選手を派遣し、各国のシニアゴルファーと親睦、国際交流を図ってきた。ゴルファーは、ともすれば、所属倶楽部内の付き合いに閉じこもりがちだが、同協会は、ゴルファーの交流を日本全体、そして海外にまで広げ、各会員がベテランゴルファーとしてゴルフ界で模範的な存在となることを目指している。
日本シニア・ゴルファース協会が設立されたのは、1962年、アメリカのシニア・ゴルファース協会から、日本ゴルフ協会(JGA)に親善大会開催の申し入れがあったことがきっかけだった。その年の10月、箱根カントリー倶楽部で第1回日米親善ゴルフ大会が開催され、同大会が隔年で開かれることも決まったため、日本のシニアゴルファーを束ねる組織として翌年、発足した。中村寅吉、小野光一両プロによる日本チームが1957年、霞ヶ関カンツリー倶楽部でのカナダカップで優勝し、第1次ゴルフブームにわいていた時期に当たる。
初代会長は、当時、JGA副会長でもあった野村駿吉氏。イギリスR&Aで日本人初の正会員になるなど、戦後、日本のゴルフ界が世界の舞台に復帰するために尽力した人物だ。野村氏は、「ゴルフは、ルール、マナー、エチケット、そして思いやりによって成り立っている」という言葉を遺している。
「協会には、今もこの野村さんの精神が息づいています」と、同協会理事の武内次男さん。「協会の競技などで各地の名門コースを回らせていただいた時、先輩から『そのゴルフ場のエチケット、フェローシップの部分がどうなっているかを、よく観察することが大事だ。それを自分の立ち居振る舞い方の参考にすると同時に、学んだことを自分の倶楽部に持ち帰るように』と教育されたものです」と話す。確かに、協会主催の競技は、普段はなかなかラウンドできない名門ゴルフ場で開催されている。参考になることは多いだろう。
協会に入会するには、まず55歳以上の男性ゴルファーであること。希望者は、協会会員2人の推薦をもらった上で、各地区支部の入会審査会を経て、理事会の審査を受けることになる。浅井義久理事・競技副委員長は「以前は、自分の所属倶楽部で役員、委員を務めていたことも条件でしたが、今は競技に真面目に取り組んでこられたなど、周囲に認められる人格が備わっている方なら入会できるようになりました」と説明する。
協会は、2011年に一般社団法人となり、毎年4月に創立記念大会、6月に春季大会、10月に秋季大会を開催して、会員間の親睦を図っている。さらに、隔年開催の「日米親善大会」、毎年開催される「ワールドシニアチャンピオンシップ」への選手派遣も事業の柱になっている。「私自身の経験で言うと、大会で一緒に回った人と親しくなり、『また、今度、ご一緒にラウンドしましょう』と、交流、人脈が広がっていったことが大きな財産になりました」と武内理事は話す。
今の悩みは、会員数の減少だ。かつては450人ほどいた会員が、現在は220人ほど。このため、全国に地区支部を置き、主催競技会を沖縄を含む全国各地で開催するなど、活動の範囲と会員の輪を広げる努力をしている。だが、会員の高齢化などもあって、なかなか増えないのが現状という。
武内理事は「我々の大先輩たちは、代々、協会の活動によって、日本のゴルフ界を良くしよう、正しい方向に導こうとされてきました。この根本精神を踏まえながら、ゴルフの楽しさ、喜びを一緒に分かち合える仲間を増やす方策はないかと考えています。例えば、会員の奥様や友人も参加できる大会にし、協会の存在と活動の意義を広く知っていただくとか」と話し、浅井理事は「時代の流れに合わせ、女性会員の加入も、いずれ検討課題になるかもしれません」と加えた。
60年以上前、日米のシニアゴルファーによる交流から生まれた協会が、令和、そしてその先へ。若いゴルファーの増加などによって、マナー、エチケット、ドレスコードなどが様々に議論されている今だからこそ、深い知識を持ったシニアゴルファーが各倶楽部の枠を超えて集う組織の存在意義は大きい。
(情報シェアリング部会委員・髙岡和弘)