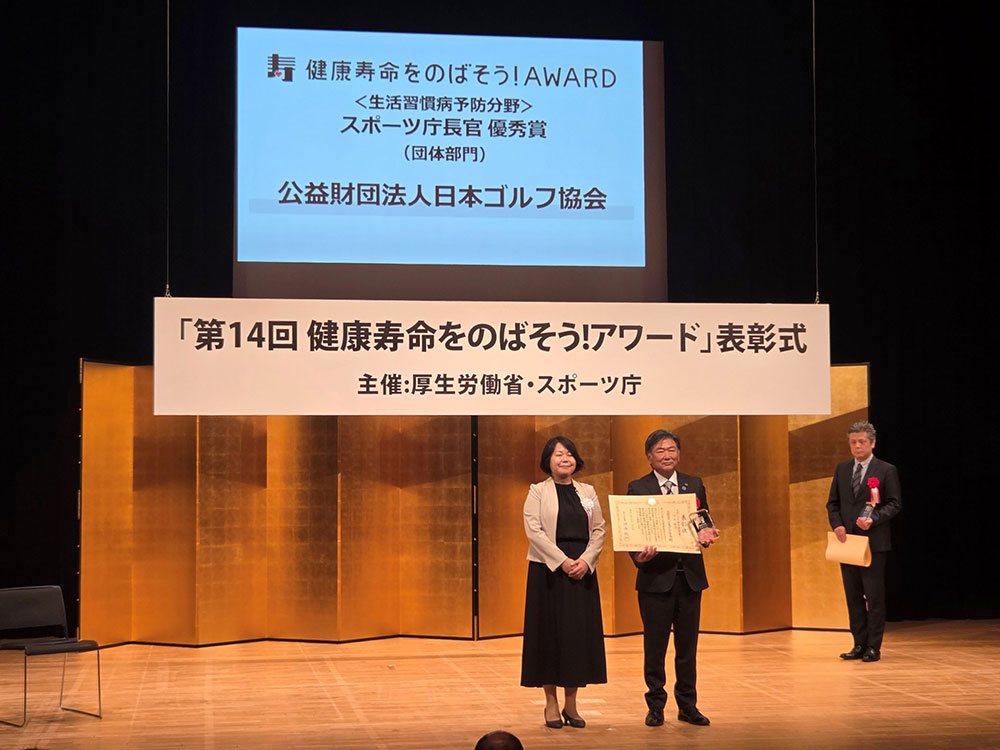ゴルフと体、健康について、科学的な視点から徹底的にアプローチした書籍の「ゴルフとからだ 健康科学へのApproach」(アイ・ケイ コーポレーション)が今年4月に発刊された。
大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科の平尾磨樹教授が中心となり、同大学スポーツ科学科の只隈伸也教授ら、それぞれの分野の専門家が編集、著作、分担執筆を担当してまとめられている。「ゴルフ関連の書籍において、これほど科学性・専門性・多様性・公平性を踏まえた解説書は我が国ではほかに見当たらない」とはしがきに記された著作について、平尾先生と只隈先生にお話しいただきました。
――まず平尾先生にうかがいます。著作の各章のタイトルやテーマを見ますと「ゴルフと健康、ウェルビーイング」「ゴルフと寿命」「ゴルフと認知機能の関係」「ゴルフに関係する骨と関節」「ゴルフとエネルギー消費」「ゴルフと筋力トレーニング」など広範囲にさまざまな視点からゴルフと体、健康について記されています。こうした本をまとめることになった動機を教えてください。
平尾磨樹先生 大学で授業をすることになって、スポーツ医学の授業にゴルフを取り入れてみることにしました。ただ、いろいろハードルもありましたが、スポーツ科学科でゴルフ実習を担当している只隈先生に相談して野球場や体育館でもできて、ものを傷つける心配もないスナッグゴルフを実施することにしました。学生たちの反応はすこぶるよくて、「こんな楽しい授業はない」という感想が多くありました。授業ですから、ただスナッグゴルフをするだけでなく、ストレスの値や体の変化について、唾液アミラーゼや心拍変動(心拍間隔の微小な揺らぎ。自律神経の働きをみる指標)などのデータをとって検証してみたら、ストレス低下が示唆される結果が得られました。ゴルフと体の変化というのが面白いと思って、授業の教科書としても使えるようにまとめてみようと考えたのがきっかけです。
――只隈先生は、学生時代に大東文化大の長距離選手として箱根駅伝に4年連続して出場、3年時には花の2区で区間賞を獲得するなどエースとして活躍されました。今回はゴルフに関する書籍の編集にどう関わられたのですか。
只隈伸也先生 大学の陸上部監督として長距離選手指導の現場から離れてからは、スポーツ科学科で教員として学生を教えています。ゴルフもその対象として授業に取り入れています。医科学の授業でゴルフをやることに最初は懐疑的だったのですが、内科医としても活動している平尾先生が医科学的な視点からゴルフの良さとか健康への影響などについてエネルギッシュにお話しされて、スポーツ科学の分野とも多くの接点があることを再認識しました。「ゴルフって楽しくて健康にもいいよね」という考え方が基本にあって、医科学とスポーツ科学がつながる。そんな中で、平尾先生の多彩なつながりから、ゴルフと健康の本を書いてみないかという話が持ち上がってきたのが1年ほど前のことです。後は、さまざまな人々を巻き込んでいく平尾先生の行動力でどんどん進んでいって、今年4月の発刊となりました。

――平尾先生とゴルフの出会いは、そして現在のゴルフライフは。
平尾先生 高校時代に父親の仕事の関係でアラスカに住んでいました。父と兄がゴルフ好きでアンカレッジの隣にあるパーマー市のゴルフ場によく一緒に行きました。そのときから、ゴルフはとてもウェルビーイングなスポーツだと感じています。その後、10年間ぐらいアメリカにいて、日本に戻りましたが、途切れ途切れになっていたゴルフを本格的にやるようになったのは5年ぐらい前からです。コロナ禍がきっかけでした。ツアープロの方に教えていただく機会もあり、筋力トレーニングをしたりして、ゴルフをやることによって起こる体の変化を感じて、それが面白くて、この本の作成にもつながってきています。
――只隈先生は。
只隈先生 現役引退後に高校の指導者になった1997年頃、周りの人に勧められてゴルフを始めました。競技志向のゴルフに本格的に取り組むようになったのはやはりコロナ禍のころからです。
――著書の中では、国内外のさまざまなデータが引用されています。
平尾先生 たとえば、「ゴルフと寿命」の項ではスウェーデンの生涯スポーツとしてのゴルフの効果に関する報告や、アメリカのチャンピオンズツアーのゴルファーを対象にした研究などが紹介されています。
私の医師としての専門は血液内科で、論文や報告書といった文献を研究して治療を提案するのが大切な仕事です。そんな中で今回、ゴルフに関するさまざまなデータ類も注視することになってきたのだと思います。—こうしたデータに基づき、“安全に長く続けるコツ”と、授業・部活・地域でそのまま使える実践ヒントを示しています。
――この点について只隈先生は。
只隈先生 「ゴルフが健康に良い」ということは、誰もが何となく感じていることだと思うのですが、その効果を科学的に裏づけるためには、さまざまな角度からのデータや報告によるエビデンスを積み重ねていく事が大事だと考えています。
――平尾先生がゴルフを授業にとりいれる過程で気づかれたことや、感じられたことは。
平尾先生 もっと気軽に大学でゴルフを始めることができればと感じました。最初はいくつものハードルがあって大変でした。うちの大学は恵まれていて、スナッグゴルフの用具などを揃えることができましたが、まず用具の問題などを乗り越える作業が大変です。ゴルフに入っていける門戸が広くなれば、それだけゴルフと健康について実感できる機会が増えていくと思うのですが。
――この点について只隈先生は。
只隈先生 やはり道具を準備するところが大変です。道具を持っている学生はほとんどいません。私が世話人として所属している大学ゴルフ授業研究会では、中古クラブなどを提供するシステムがあり、それを活用させていただいています。また、普通に18ホールをラウンドするだけでなく、3ホール、4ホールだけラウンドしてみるとか、より実践しやすい方法も取り入れています。こうした取り組みも含めて、地域や施設の協力関係を充実していくことが大事だと思います。
――平尾先生が医科学的な視点で強調したい点はありますか。
平尾先生 障害者ゴルフの専任ドクターをやってみて感動しました。後遺症のために麻痺が残る人がゴルフによって筋力が回復していくような過程をみて、ゴルフは歩くことに加えて筋力トレーニングの要素もあると実感しました。こうした点も含めて、歩くだけではないゴルフの健康への良さをもっと、さまざまな視点で実証していくことができればと考えています。
大阪公立大学や全米女子プロゴルフ協会の先生たちと一緒に、ゴルフと健康についてさまざまな実証実験を進めてエビデンスとなるデータを集めています。
――この本の第2弾も考えていらっしゃいますか。
平尾先生 この本を第1弾として、次の第2弾では、もう少し分かりやすくて、気軽に手にとれるような本にしたいと考えています。また、ゴルフを始めるときや継続するときに困ったときの処方箋になるような内容も含めたいと思います。
▽略歴
平尾磨樹(ひらお・まき)
アメリカのタフツ大学で生化学、カリフォルニア大学デイビス校で生理学を研究し、ワシントン大学で生体分子構造設計学を専門として博士(化学)を取得。その後、北海道大学医学部卒業。大東文化大学教授として講義を受けもちながら、週2回は内科医としてクリニックで患者の診断、治療にあたっている。
只隈伸也(ただくま・しんや)
大東文化大陸上部で長距離選手として活躍。1985年から4年連続で箱根駅伝に出場した。現役引退後は仙台育英高陸上部監督、大東文化大陸上部コーチ、監督を務めた。指導の第一線から退いてからは、スポーツ・健康科学部スポーツ科学科教授として学生の指導やスポーツ科学の研究にあたっている。
▽本の概略
「ゴルフとからだ 健康科学へのApproach」
(A4版 本文230ページ、索引、ワークシート付き)
前半の総論では、スポーツの体と健康への貢献についてテーマごとに解説。後半の各論ではゴルフによる健康増進効果について生理・代謝との関係や神経・認知面からもアプローチ。障害者と高齢者に対するゴルフの治療的活用、ゴルフルールとエチケット、ゴルフに必要な基本的技術と知識についても詳しく解説している。健康づくりに活かしたいゴルファー、教員・コーチ、医療・リハ関係者に最適。読めば、安全で効果的な実践と長く続けるコツが身につき、ウェルビーイング向上に直結する。
取材・文/古谷隆昭(情報シェアリング部会委員)